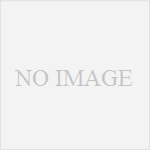
オルビスディフェンセラで乾燥肌にアプローチ!内側からしっとり潤う飲むスキンケア
乾燥肌に悩む方々の中で、注目を集めているのが「オルビスディフェンセラ」です。市販や薬局、ドラッグストア、マツキヨ、ドンキなどの一般的...
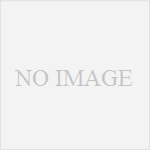
乾燥肌に悩む方々の中で、注目を集めているのが「オルビスディフェンセラ」です。市販や薬局、ドラッグストア、マツキヨ、ドンキなどの一般的...
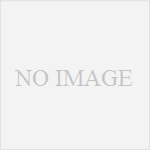
ライースリペアは、美容液や化粧品市場で注目を集めているアイテムの一つです。その特徴的な成分や使い方、口コミ、そして通販の最安値について詳しく...
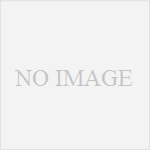
ホロベルシャンプーは、髪と頭皮の健康に特化した商品で、その効果は口コミで広まり、多くの人々がその魅力に惹かれています。この記事では、ホロベル...
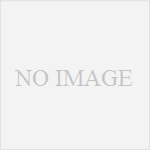
肌の美しさを保つために、発酵化粧品が注目されています。この記事では、発酵化粧品について深掘りし、特に日本の人気ブランド「米肌」に焦点を当てま...
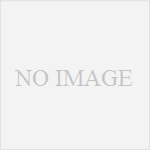
胡蝶蘭は、その美しい花姿と長い花期で人気を集める洋ランの一種です。その鮮やかな花びらは、まるで舞い踊る蝶のように優雅で、贈り物としても最適で...
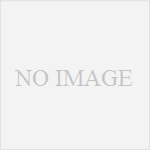
シボヘールというサプリメントを聞いたことがありますか?このサプリは、植物由来の成分で、体内の脂肪の吸収を抑えることができると言われています。...
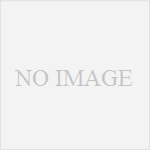
赤ちゃんとのレクリエーションは、親子の絆を深めるだけでなく、赤ちゃんの発育や感情の発達にも良い影響を与えます。以下に、赤ちゃんとできるレクリ...
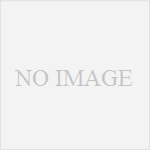
子育ての旅路において、赤ちゃんの成長と発達は不思議で素晴らしいものです。その一環として、赤ちゃんの発達教室は貴重な存在となっています...
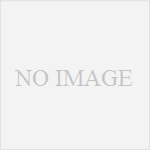
現代の社会で、女性は自信を持ち、健康で美しい生活を送りたいと願うことは当然のことです。女子力とは、外見だけでなく内面から輝く自己肯定感や魅力...